具体的な活動内容

1)不登校・引きこもりの受け入れ・支援
■受け入れ施設運営
不登校や引きこもりの子供たちを無料で受け入れ、滞在できる施設を通年、毎日運営した。述べ600人以上の子供やその保護者を受け入れることができた。
適宜、参加者の話し相手になったり、相談に乗った。希望する児童には適宜、勉強を教えた。
■共同作業を通じた社会復帰支援
共に畑を耕したり種を撒いたりといった農作業や活動場所管理のための草刈りなど、共同作業を通して社会復帰するための支援を行った。
不登校児童の場合は親も活動に参加することが多く、スタッフと共に親も活動しているので児童も作業に混ざりやすい。皆での共同作業においては不登校の原因の大きな一つである親の過干渉も抑制される。
2) 森の放課後倶楽部
前年度とほぼ同じ感じで活動を継続した。
毎週金曜日放課後、大自然のフィールド内において、学校や公園ではできない冒険的な体験ができる場を提供した(参加者述べ210人)。登校している子も不登校の子も、また違う学校同士でも仲良くなる機会を持ってもらった。
学校や公園では少しでも危ない遊びはNGとされ、制限された遊びしか経験していない子にとって、自然の中でのびのびと遊ぶのは豊かな体験となったようだ。木に登ったり崖をよじ登ったり、走って転んで擦りむいたり、、、多少の怪我はしつつも元気に遊んでくれた。
栗やタケノコを収穫したり、どんぐりを拾ったりと季節折々の自然の楽しみ方を伝え、参加者に楽しんでもらった。
また、寒い冬の季節は焚き火をしてマシュマロを焼いたり、ココアを温めて飲んだりしたが、火の扱いも参加者たちには好評だった。
小さいお子さんの場合には保護者さんにも同伴してもらうが、その保護者同士の交流も図った。保護者の中には他の放課後クラブのような所に参加している方も多く、お互いに放課後クラブの紹介をし合ったり、参加し合ったりしてくれた。
3)鶏小屋制作及び柵の設置
鳥小屋を設置し、二羽の鶏を飼育。活動参加者たちに飼育を手伝ってもらった。
農作物を作るために荒れ地を開墾して畑を作り、イノシシやシカなどの野生動物が侵入しないための柵を作成。 700m2
活動成果及び今後の課題
=活動成果=
概ね予定通りに活動することができ、下記のような成果も得られた。県内のフリースクール運営者同士の連絡会を構築し、県の教育委員会や職員と定期的に話し合う関係を持てるようになった。その活動を通してフリースクールへの通学にも定期割引が適用できるようになったという成果が得られた。
活動参加者が当団体の有料サービスである自然体験や田舎暮らし体験・宿泊などにも参加してくれるケースが増え、収入機会が少し増えている点は昨年同様。
1)不登校・引きこもりの受け入れ・支援
学校に行きたくなくなるような子供たちは人前で失敗することに対して臆病であったり、成功体験が乏しく、人に褒められたり感謝されるイメージが湧きにくい場合が多いのだが、これらの共同作業を通して人の役に立つことを実感してもらえたのは大きな自信形成になれたと思う。
2) 森の放課後倶楽部
喜んでくれたのは子供たちだけではなく、親御さんたちからも凄い感謝された。制限なくのびのびと子供たちを遊ばせることができる場を渇望する親は多いようだ。
3) 鶏小屋制作及び柵の設置
柵を設置したことでシカやイノシシによる作物の損害も抑えられ、活動に使える土地が増えた。鶏を飼育することで、癒し効果が得られたり、虫を怖がる子供でも鶏が喜んで食べるのを知ると虫を捕まえ始めたりと、これまでの殻を破るきっかけにもなった。
=今後の課題=
1)のような弱者支援的活動においては参加者からの参加費を徴収しにくく、経営的な課題は未だに残ってはいるが、活動に興味を持つ人は着実に増えており、収益は向上してきている。今後、企業協賛を視野に入れた声掛けも進めていきたい。
この活動は公益財団法人 大和証券福祉財団の令和2年度(第3回)子ども支援活動助成を受けて行いました。


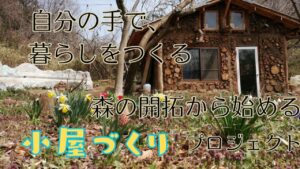




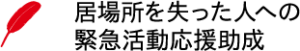
コメント